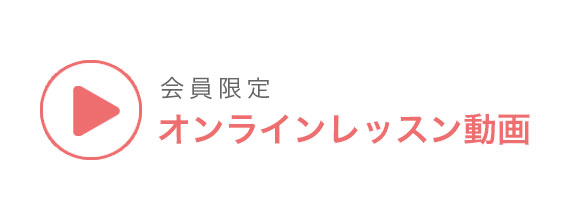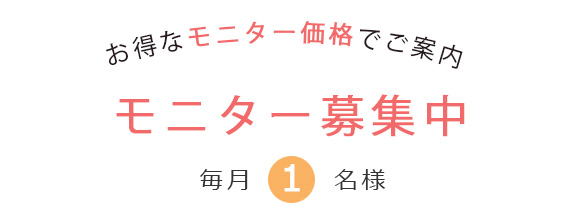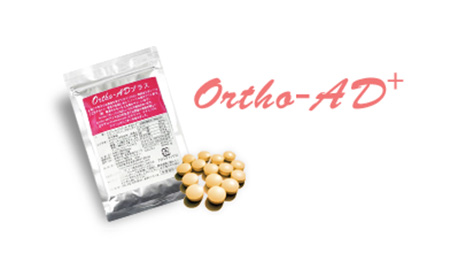ビタミンB
生きるたにエネルギーをつくるのに欠かせない栄養素 ビタミンBは、互いに協力し合い働くので、B1・B2・B6・B12・ナイアシン・パントテン酸・葉酸・ビオチンの8種類。 ビタミンB群で、摂ることをお勧めします。 ・エネルギー代謝 ・神経伝達物質 ・コレステロール調整 ・抗炎症作用 などに関係しています。
各種Bの働き
■ ビタミンB1(チアミン) 1. 糖をエネルギーに変える補酵素 2. アルコールの代謝に関与 3. 脳の働きに関与 4. 神経の働きを正常に保つ etc... 脳の発達や神経機能に密接に関わり、アミノ酸の代謝にも関わっています。 疲労や今は余り耳にしない脚気の回復に働きます。 そして、免疫系機能の維持に重要な関わりを持っています。 ■ ビタミンB1(チアミン)
1. 脂肪をエネルギーに変える補酵素 2. 過酸化脂質の分解酵素 3. 脳と肝臓の働きに関与 4. 皮膚や粘膜の代謝に関与(成長の促進) etc... 成長ホルモンの合成にも深く関わり、不足すると口内外の炎症、皮膚炎、目の充血、成長障害に繋がるリスクが高まります。
■ ビタミンB6(ピロドキシン) 1. アミノ酸代謝や神経伝達物質の生成の補酵素 2. カラダのタンパクの合成や造血に関与 3. 脳の働きに関与 4. 神経伝達物質の生成や抗アレルギー作用に関与 5. 脂質の抗酸化に関与 免疫系機能の維持に重要で、欠乏すると口角炎、皮膚炎などが起こりやすくなります。 長期間大量摂取すると知覚神経障害、ショウ酸腎臓結石などの恐れがあります。 ※腸内細菌によって合成され通常は不足する事はありません。
■ ビタミンB12(コバラミン) 1. 神経の正常な働きを維持 2. ヘモグロビン、赤血球の合成の造血作用に関与 3. タンパク質の代謝、核酸の合成に関与 4. 脳の発達に関与 神経や血液細胞の健康を保ち遺伝子物質であるDNAの生成を助ける栄養素。 しっかり動物性食品を食べていれば欠乏することはありませんがベジタリアンや胃を切除している場合は悪性貧血になりやすくなります。 ■ ナイアシン(ビタミンB3) 1. エネルギーの生産、脂質や糖質の分解に関与 2. 皮膚、粘膜の炎症を防ぐ 3. 神経症状を防ぐ 糖代謝、脂質代謝、アミノ酸代謝における多くの酸化還元酵素の補酵素の構成成分で、ステロイド合成にもかかわっておりブドウ糖を脳のエネルギーに変える際の補酵素になります。 ■ パントテン酸(ビタミンB5) 1. タンパク質、脂質、糖質の代謝に関与 2. 神経、副腎皮質の機能を正常に保つ 3. 皮膚や毛根に栄養を与える 動植物食品に広く含まれ、腸内細菌からも合成されるため通常の食生活では不足する事はありません。 糖代謝や脂質代謝の反応、皮膚や粘膜の維持、神経や副腎皮質の機能維持にも関わっています。 不足した場合、成長停止、食欲不振、皮膚炎などが起こります。 ※過剰症は知られていません。 ■ 葉酸 食品中に広く含まれていて、核酸合成やアミノ酸代謝で重要な役割を担っています。 腸内細菌からも合成されるため欠乏症はおこりにくいですが、不足した場合は貧血を起こします。 ※過剰症はほとんどないと云われています。 ■ ビオチン 1. 皮膚の健康を保つ 2. 筋肉痛の緩和に関与 3. 白髪、薄毛を予防 食品中に広く分布しており、腸内細菌からも合成されるため欠乏症は起こりにくいと言われ糖新生、脂肪酸の合成、アミノ酸代謝などに関わっている。生の卵白を大量に摂取すると、腸管からの吸収が阻害され、皮膚炎や脱毛、体重減少などが起こります。
体調に合わせてサプリの選び方 !!
オーソ21+ ビタミンCが基本 ※オーソ21には、ビタミンCが適量入っていますがVCの働きは多岐にわため ■ 体調にあわせて以下を組み合わせをオススメ
・ヘモグロビン低下 7 ミネラル(食事では、淡白摂取) ・疲労 ビタミン ・抗酸化 7ミネラル・ビタミンE ・腸内環境 フラクトオリゴ糖 など。 上記以外に、ご不明な点、ご質問があればお気軽にお問い合わせください。 ご相談内容によっては、プラスしなくても良い場合もありますのでご注文前にご相談ください。 パーソナルレッスンまたは、私用で直ぐに対応できないこともありますので予めご了承くださいませ。 必ずご返答させて頂きますので宜しくお願いいたします。
サプリメントとは
生きていく上で無くてはならない栄養素(正分子)を手軽に摂取出来る物のことを言います。 (人間に必須の物質で、3度の食事で摂取することが困難なもの) ※当サロンで扱っているのサプリメントは、総合体力研究所のものです。 お届けはメーカー(総合体力研究所)からのお届けとなります。 正分子療法についてさらに詳しくお知りになりたい方は、こちらをご参照ください。
正分子とは
生命維持に、必要不可欠で自分では造れない物質を分子レベルで正分子といいます。 (薬、環境ホルモンなどを異分子といいます) その正分子は50種類あり、それをきちんと摂取することでカラダの健康を維持しようと考えるのが正分子療法といいます。 正分子の中には、13種類のビタミンが含まれており、これらは普段の食事だけでは必要量を摂取するのが難しいものもあります。